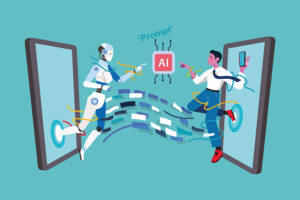
生成AIの登場により、表現の世界が揺れている。絵、音、文章──人が時間と労力をかけて紡いできた創作が、数秒で出力される時代。誰もが驚き、戸惑い、魅了され、そして少しずつ“慣れて”きた。だが、その「慣れ」の裏側で、私たちは何を変えようとしていて、何を失いかけているのか。生成AIという地球人類の新たな成果物をどう捉えるか、というところから始めたい。生成AIは、単なるツールではない。それは、価値観や表現観を静かに問い直す存在であり、人類が自分たちの「創るとは何か」「伝えるとは何か」を見直すきっかけになっている。この現象を「進化の脅威」ではなく、「AIの進化によって、人間もまた進化できる」という可能性として捉えている。ただし、それは無自覚に進んでいくものではない。むしろ、今こそ意識的に“関係性を見直す”必要がある。ここでのカイゼン考察は、ある意味でひとつの“始まり”である。
最初に宣言しておくと『AIは活用すべきである』というのが自分の基本的な立ち位置である。人類が進化するのを牽引してもらうためにAIは徹底的に先に行ってもらうべきものと考えているからだ。だから人類はそれに最大限の協力をすべきであり、協力を拒むことに意味は無い。衣服を人類が取り入れたようにAIが人類に浸透していくのは既定路線だ。遅かれ早かれなら、早いほうが良い。「ゆっくり丁寧に付き合ったほうがいい」という方もいるだろうがAIの恩恵を渇望している不幸な方々は沢山いるのも事実だ。どちらにせよ浸透するのは自然現象ぐらいに思ったほうが良い。AIを創造して世に広めようと奮闘している人たちを憎むことはできないだろう。すでに人類はAIの恩恵に浸っているのだ。だが、生成AIというツールは中途半端な存在であり道具の域は超えない。すぐさま超えてしまう予兆はありはするが、今のところは人間が使いこなして真価を発揮するピカピカの単なる道具なのである。世の混迷は、新たな強力な道具を使いこなして、自らの人生にメリットを見出そうという個々が大量に存在するからだ。AさんにメリットがあればBさんにデメリットが生じるかもしれない。そういうものだ。この状況のままでのセーフティネット構築はおそらく間に合わないだろう。多分に犠牲者が出る。少なくとも牛丼大盛を普通盛にしなければいけない影響は出る。ならば変革に対して全体で対応したほうが良い結果が早めに出せるだろうと思う。もちろん、個の営利活動を裏切扱いすることは厳禁だ。まずは新たな基準を整えることが鍵となるだろう。
まず、対象とするのは、「絵」と「音」だ。どちらも人の感覚に深く関わり、表現者の存在を強く意識させるジャンルである。アートとしてのセンスが問われる成果物。今まさに、そこにAIが入り込み、表現と受容の構造が揺らぎはじめている。一方、「文章」については少し事情が異なる。芸術性を問われる側面もあるが「文章」は情報伝達や構造性を求められる場面が多く、受け手が「誰が書いたか」を重視しないことも多いと思われる。ストレートに意図が理解できるため、その先に解釈がある。つまり二段階であることから障壁が二つあるということだ。障壁とは「人間が冷静に判断する機会」となる。少なくともアイデアの提供という面から言えば、生成AIを語るには「文章」が最重要のテーマと考えているが、分析するに様々な意味合いで直感的な「絵」と「音」に絞って考えていくことにする。特に「絵」については取り組んでいる人が多く、さらに公開されている数も多く、ネットに勤しむ者なら誰しもが大量に目にしているはずだから分かりやすいと思うのだ。
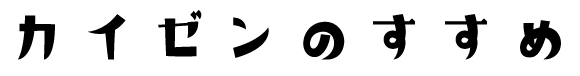
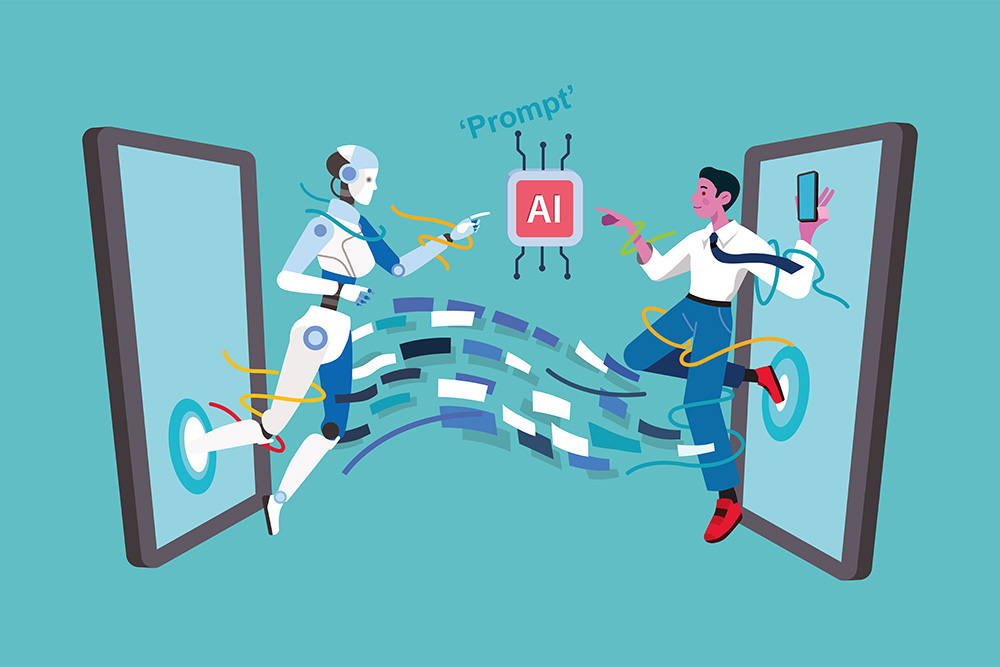


コメント