
生成AIによって誰でも“それらしい絵”が作れるようになった。その一方で「描く」という行為そのものを大事にしてきた人たちが戸惑いや怒りを感じている姿も目にする。けれど、この反応は単純に「AIを肯定するか、否定するか」という話では片づけられない。なぜなら、人が「絵とどう関わっているか」は一様ではなく、描く理由や動機、目指しているものが、実にさまざまだからだ。絵を描いている、あるいは描きたいと感じている人々を、目的や立場によっていくつかのグループに分けてみると、生成AIとの関係性が見えやすくなる。現状で見られる層を整理してみたい。
1. 技術を極めたい人
- 描くこと自体が喜びであり、成長を実感したい
- 模写・デッサン・構図・色彩理論などに深い関心を持つ
- AIの自動生成は「努力を飛ばす」行為に見えて不満を感じやすい
→ 生成AIとの摩擦が大きい。技術を磨く意義が軽視されることへの反発が根底にある。
2. 自己表現として描く人
- 描きたい感情や世界観がある
- 上手さより「自分らしさ」を大事にしている
- AIを使うかどうかは、その目的に合うかで判断する
→ 生成AIを使うことに柔軟。補助的なツールとして歓迎する場合も多い。
3. プロとして描く人
- 仕事として絵を描く(イラストレーター、漫画家など)
- クライアントワークや商業性を強く意識している
- AIによる「低コスト・大量供給」によって競争環境が変わりつつある
→ 職業としての危機感を持つ。AIによって「価値のある絵」がどう変わるかが課題。
4. 描けないけれど絵を創りたい人
- 発想や世界観はあるが、技術的に表現できない
- 人間の絵描きとコラボしたい人もいれば、AIに補助を求める人もいる
- 表現手段として「描く」ことにこだわりはない
→ 生成AIを積極的に活用する層。ただし、人間との共創を望むケースも多い。
5. 評価や承認を求める人
- SNSで「いいね」を得たい、自分の作品を見てほしい
- 上手さや独自性より「映えるかどうか」が重視される
- AIによる生成も選択肢のひとつ
→ 成果主義・即効性重視の傾向があり、AIの導入に抵抗は少ない。
とまあ、こんな感じで「絵を描く」という行為の中にも、多様な意図と目的が存在しているだろう。だからこそ「AIを使うかどうか」という問いは、本来は「その人が何を大事にしているか」によって答えが変わってしまっても仕方がないのだ。生成AIの登場によって「絵が描けるかどうか」よりも「絵とどう向き合いたいか」が問われる時代になった。ツールの進化が、人間のあり方を問い直す。だから必要なのは「使う/使わない」という単純な選択ではない。自分の動機や価値観に即した関わり方を選べること。そしてもう一つ重要なのは、他者の関わり方を否定しないことだ。
- 技術を積み重ねたい人は、その営みを続ければいい
- 表現の幅を広げたい人は、AIと組んでみてもいい
- 人の手で描かれたものに価値を見出す人がいてもいい
- AIが生むスピードやアイデアに魅力を感じる人がいてもいい
大切なのは「どの立場も、ある種の誠実さを持っている」ということを忘れないことだ。生成AIが広がっていく中で、創作の地図は確実に変わっていく。だが、その地図の中でどこに立つかは、私たち一人ひとりが選べる。それが、いま必要な『カイゼン』の基礎になるはずである。
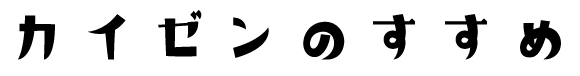

コメント